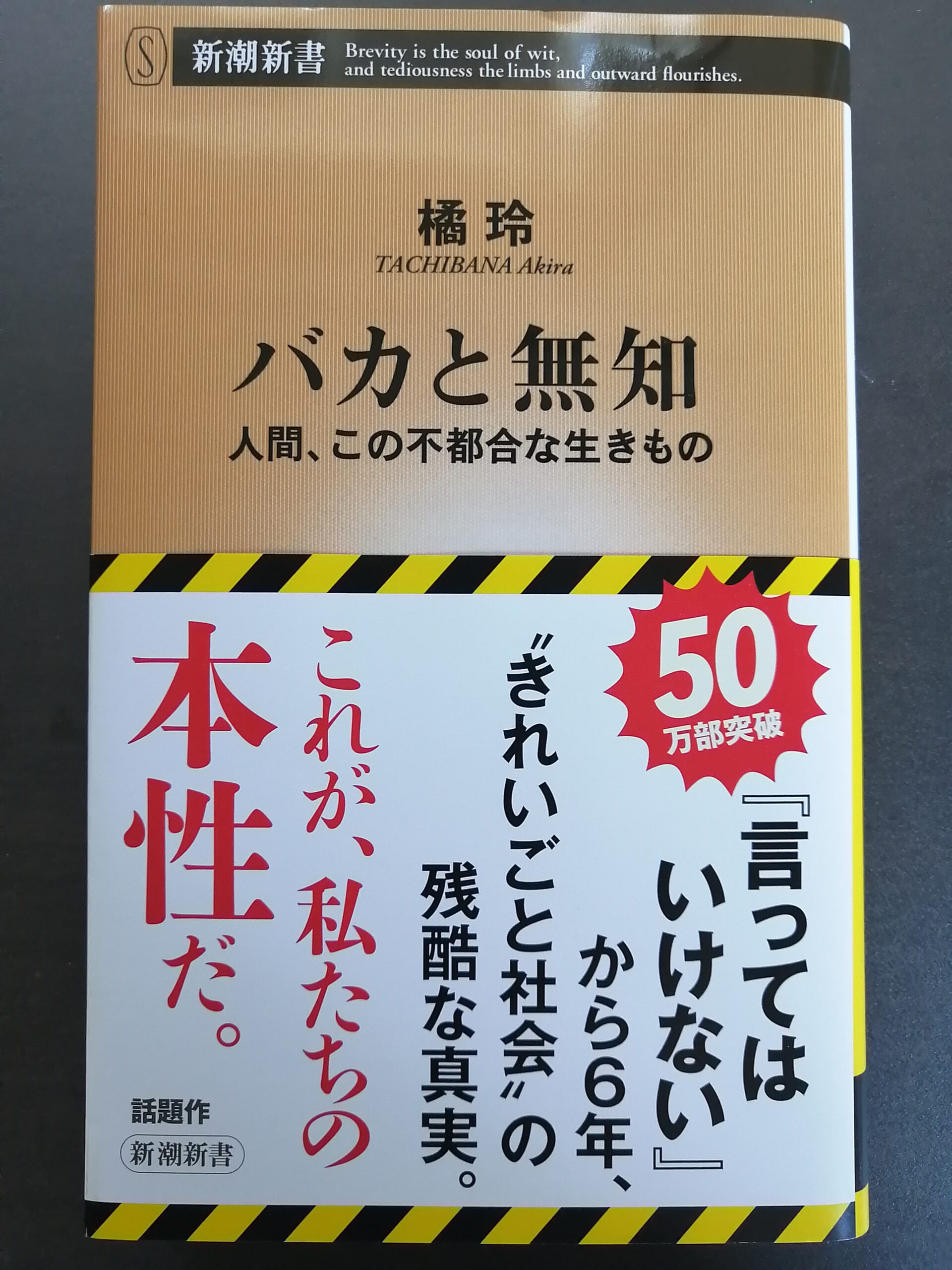橘玲先生の話題作。バカと無知。
このインパクトのある題名に気になる方も多いと思います。
今回は、そんな橘玲先生の書かれた「バカと無知」の、個人的に印象に残ったポイントを3つ紹介していきます。
正義は最大の娯楽!?
近年の脳科学では、脳にとって、自分よりも劣った者は報酬で優れた者は損失と感じることわかった。また、ルール違反をした者を処罰するときにも脳の報酬系が活性化(快感を感じる)ことが確認されている。
「正義」を脳にとっての快感にしておけば、ひとびとは嬉々として集団の和を乱すものを罰するようになる。すべての生き物は、快感を求め苦痛を避けるようにプログラムされており、脳にとって優れた者は損失なのだから、不快感から逃れるには、自分よりも優れた者を蹴落とせばいい。噂話の目的は、自分よりも上位の者を引きずり下ろし、下位の者にマウントをとって自分を目立たせること。これは聞こえが良い話ではないが、そこに「正義」を紛れ込ませると、自分の行為を正当化できる。
ネットニュースでいちばんアクセスを集めるのは芸能人と正義の話題で、メディアが有名人のスキャンダルで、見ている人々の怒りをかき立てるのは、現代社会にとって、正義が最大の娯楽(エンタテインメント)だから。
幸福度を高めるには、世の中に惑わされず、他者に「不道徳」のレッテルを貼って安易に批判せず、イヤなことがあっても「そのうちいいこともあるさ」と楽天的に考えること。
バカと無知
バカ=知らないことを知らない
無知=知らないことを知っている
バカの問題は、自分がバカであることに気づいていないこと。(ダイニング・クルーガー効果)
自分の能力についての客観的な事実を提示されても、バカはその事実を正しく理解できないので(なぜならバカだから)、自分の評価を修正しないばかりか、ますます自信を持つようになる。
バカは他人事である、と思ってもいられない。なぜなら、バカは原理的に自分がバカだと知ることはできないから。私も、そしてあなたも、自分がバカと知らないだけなのかもしれない。
能力が低い者が過度な自信を示すことで、能力の高い者の自信が揺らぎ、決定が変わる。これが「バカに引きずられる」メカニズム。
原理的に考えれば、バカを排除する以外に、「バカに引きずられる効果」から逃れる道はない。ワンマン企業が成功するのは、独裁者の意思決定によって、その効果を避けられるからなのかもしれない。
すべての記憶は偽物
近年の脳科学の最も大きな発見のひとつは、脳には記憶が「保存」されていないこと。脳にハードディスクが埋めこまれているのではなく、なんらかの刺激を受けたとき、そのつど記憶が新たに想起され、再構成される。記憶はある種の「流れ」であり、思い出すたびに書き換えられている。
記憶とは原理的には、ニューロン間の「つながりやすさ」と「つながりにくさ」の組み合わせでしかない。
脳科学の最先端では、記憶に影響を与える研究が進んでおり、将来的に記憶を書き換えることができるようになるかもしれない。そうなればトラウマに苦しむことはなくなるが、そのとき、「わたし」とはいったいなにものになるのだろうか。
まとめ
初めて本の要約にチャレンジしましたが、なかなか難しい。自分の解釈が正しいのか、そんな不安もあります。
バカと無知の違いについて読んでいて、ソクラテスの「無知の知」という言葉を思い出しました。近年の研究で証明されたことを、2000年以上も前に気づいていたと考えると、やはりソクラテスは偉大だと思いました。
また、すべての記憶は偽物というのも、アドラー心理学でも、同じようなことがいわれていたと感じました。それもこちらで紹介しておきます。
われわれの世界には、ほんとうの意味での「過去」など存在しません。過去とは、取り戻すことのできないものではなく、純粋に「存在していない」のです。(岸見一郎著 幸せになる勇気より引用)
これも心理学の世界で言われていたことですが、脳科学の世界でもそれが証明されたと考えると、心理学と脳科学は強く結びついているのだと思いました。
この記事を読んで、橘玲先生のバカと無知のことが少しでも伝われば嬉しいです。
ご覧いただきありがとうございました。